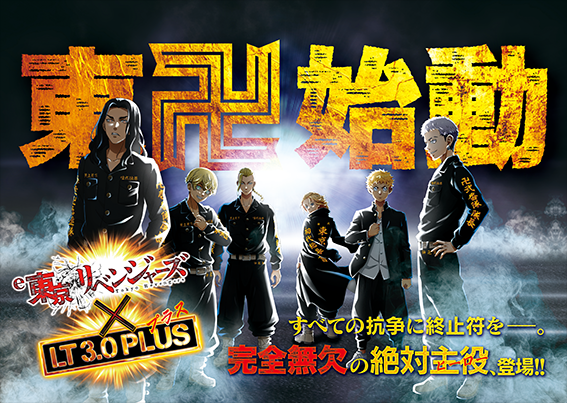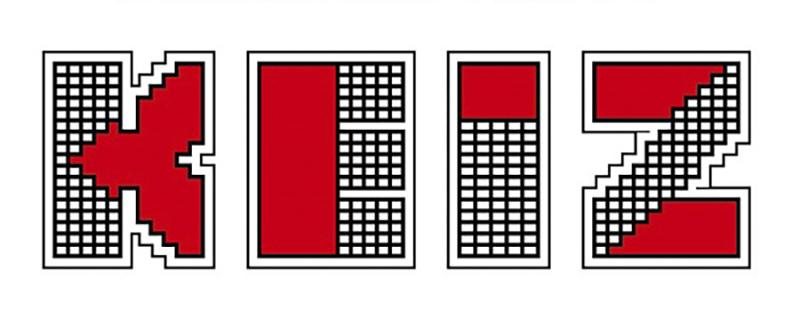No.10004759
M&Aを通して業界の活性化を|データドリブン思考で投資戦略を設計
INTERVIEW
株式会社 絆
小林慎也 代表
エビデンスベースの経営・営業をサポートする絆。同社の事業のひとつがM&Aアドバイザリー事業だ。数々の案件を手掛けてきた小林慎也代表に今後の業界活性化に向けたヒントを聞いた。(文中敬称略)
──業界メディアに登場されるのは初めてだと思いますが、まずは御社について教えてください。
小林 2019年に創業し、現在6期目の会社です。私自身は元々、遊技機商社大手に約17年在籍し、最後は事業戦略部長を務めました。他のメンバーもパチンコ関連企業出身で、プロモーションやマーケティングといった特定の領域で活躍してきた仲間たちです。それぞれの専門性や強みを発揮しながら、メーカー様とホール様に横断的なサービスを提供しています。メーカー様であれば、開発支援から販売戦略、導入後の稼働支援まで。ホール様にはマーケティングの支援、弊社開発サービスのご提供から販促の支援、それに加えてM&Aサービスが事業の中心です。いずれにしても我々は主役であるホール様やメーカー様の黒子的存在ですので、こういった表舞台に出るのは得意ではありませんが(笑)。今回はたまたま昨年M&Aの仕事をさせていただいた、マルハン北日本カンパニー様とDMM.com様の記事とご一緒にということで、インタビューをお受けしました。
──M&A事業に参入したきっかけは?
小林 全国のホールオーナー様、あるいはそれに準じる経営層の方とコミュニケーションを取らせていただくなかで、「ホール事業の拡大」「会社・事業の売却」という相談を受ける機会が多くなっていたことが大きな理由です。我々はマーケティングを得意とする会社で、独自のホール検証モデル、いわば価値算出のノウハウを有しています。簡単に言えば、一般的なエリアマーケティングに加え、パチンコホール独自の指標を組み込むことで、ホールの価値診断を客観的にできるということです。一例として「Aという法人が、Bという場所で、Cという台数でホールを運営した場合」に、どの程度の客数や粗利を獲得できるかを、かなり高い精度で導きだすことができます。
──そうした分析がM&Aのセカンドオピニオンとしても役に立つということですか?
小林 売り手と買い手が納得感を持つ価格ならば、それが適正価格とも言えるわけですが、実際には双方の要望に乖離が生じることもあります。こうした客観的な診断が、目線を揃えるある程度の基準になります。買い手法人にとっては、自社では気づけなかった出店の可能性を見出すことができます。売り手側は、既存の稼働や客数だけでは測れないバリューをつけられることもある。もちろん、逆に売り手側の条件を引き下げる材料になることもありますし、「この物件を売却することは難しい」というシビアな結果が出ることもあります。その場合は、異業種を含めて売却候補を紹介することもできます。
M&Aで産業の生産性や
付加価値を高める
──昨今のホールのM&Aに対する意欲をどのように捉えていますか?
小林 以前から引き続き、関東圏・関西圏・中京圏の中心部寄り、つまりマーケットが潤沢で将来人口の減少率が少ないエリアを希望される法人が多いですね。規模は600台や800台以上など一定規模以上が多いのはご承知の通りですが、昨今は以前ほど規模を重視する傾向は強くなくなってきました。500台クラス、あるいはそれ以下の台数でもエリアや案件によっては成約するケースが増えました。ひとつは、スマスロの好調で「パチスロ専門店」という可能性が広がったことが背景にあるかと思います。
──直近で御社が仲介を手がけたM&Aで印象に残っている案件はありますか?
小林 ホール企業ではありませんが、中古遊技機取引情報サイト大手のP‒SENSOR様とDMM.com様とのマッチングをお手伝いさせていただきました。業界の中古機売買サイトとして唯一無二の存在を築き上げてきたP‒SENSOR様にオファーを出させていただいたのが数年前の話でした。定期的に会社の課題や将来のビジョンなどをお話させていただいているうちに、オーナーとしてもP‒SENSOR事業を進化させていくにはDMM.com様の「ぱちタウン事業」との統合が大きな選択肢のひとつであるという方向に進んでいきました。最終的には両社と何度も顔合わせしながら信頼関係を築くことができ、無事成約となりました。事業をどうすれば拡張できるか、売り手と買い手が真剣に語り合う姿を今でも思い出しますし、今後のP‒SENSORがどのような進化をしていくのか、私も楽しみです。P‒SENSOR事業を保有したいという企業は多数あったのですが、最もシナジーが見込める企業を選定したという側面もありました。
──ホール企業のM&Aに関してはいかがでしょうか?
小林 昨年も多くのM&A案件に携わらせていただきましたが、直近で言えばマルハン北日本カンパニー様が買い主として成約したケースが印象的でした。マルハン北日本C様は売り手の意向に沿って柔軟にスキームを組んでくれますし、金額や時期などといった基本的な条件で折り合いがつけばスピード感を持って進めていきます。マルハン北日本C様は今、最も出店の勢いがあるグループだと思いますが、その勢いの原動力となっているのは、こうした開発力にあるのだなと、あらためて肌で感じました。
──今後はM&Aにどう関わっていきますか?
小林 「業界再編」というと大げさですが、大きな視座でみるとM&Aは産業として生産性や付加価値を高めることになり、それが回りまわってエンドユーザーにも好影響を与えます。ひいては遊技人口の維持や業界の発展にも貢献できるのではないか。そんな想いで、今後も携わっていければと思っています。
──今後、絆としてはどのような成長戦略を描いていますか?
小林 弊社はメンバーの全員が経営にも事業にもコミットしてもらうというスタンスをとっています。そのおかげで事業拡大のスピードは想定以上に早いのですが、とはいえ弊社もメンバーはグループを合わせても十数名ですので、だんだんとお受けできる仕事に限りが出始めてきました。一緒に課題解決が出来る仲間をもっともっと集めてクライアントパートナー様の発展に貢献できる黒子の極みのような会社を目指していきたいですね。

慶應義塾大学経済学部卒業後、フィールズ株式会社に入社。事業戦略部長などを歴任し、2019年株式会社絆を設立。グループ企業の取締役も兼務し、ホール企業へのマーケティング支援、メーカー企業への販売戦略支援など多方面で活躍する。
文=アミューズメントジャパン編集部
※月刊アミューズメントジャパン2025年3月号に掲載した記事を転載しました。